
保育士として職場を選ぶ際は、保育施設の種類や特徴を理解することは重要です。
「認可保育園」と「認証保育園」は名称が似ているため混同されがちですが、運営基準や働き方において違いがあります。
本記事では認可保育園と認証保育園の特徴や違いをご紹介した上で、保育士として働く際に知っておきたいポイントを整理しているのでぜひ参考にしてください。
- 認可保育園は国の基準を満たした施設で、認証保育園は都独自の基準を満たした施設
- 都独自の保育ニーズにより、柔軟な働き方やスキルの習得がしやすい
- 認証保育園は開園時間が長いため長時間保育や延長保育による負担が懸念される
当コンテンツはじっくり読むと約42分かかる充実した内容になっています。必要な要点や更新情報をいつでも確認できるよう、ぜひブックマークをしておくことをお勧めします。

保育士転職のいろは編集部
保育士転職のいろは編集部は保育人材が思う理想的な働き方を実現するために当サイトを運営しています。保育士および保育士経験者1,474名を対象とした独自アンケート調査を基に、転職サイトの実態、職場の人間関係、残業問題、年収事情など業界のリアルな声を分析・発信。編集部は保育士向けに保育園の口コミサイトほいくreviewsも運営し、保育士がより良い転職先を選択できるようサポート。Podcast番組『おつかれ保育士さん』でも配信中。著書『保育士が抱える「辞めたい」を変える』
当コンテンツについて
※当コンテンツは保育士転職のいろはが定める広告掲載ポリシー及びプライバシーポリシー・免責事項に基づいて作成・管理されています。
※当コンテンツはファーストパーティクッキーを使用しており、サイト訪問者の利便性の向上やサイトパフォーマンスの改善を目的にGoogleアナリティクスを活用しています。
※本記事に誤りやご意見がございましたら、こちらの問い合わせフォームよりご連絡ください。管理人が内容を確認後に必要に応じて内容を訂正させていただきます。
当コンテンツは構成・執筆・編集を保育士転職のいろは編集部が担当し、アイキャッチデザインの作成を外注デザイナーが担当して作成されています。
また、保育士転職のいろは編集部は以下のWebサイトに掲載されている情報や自身の知見に基づいて当コンテンツを作成しています。
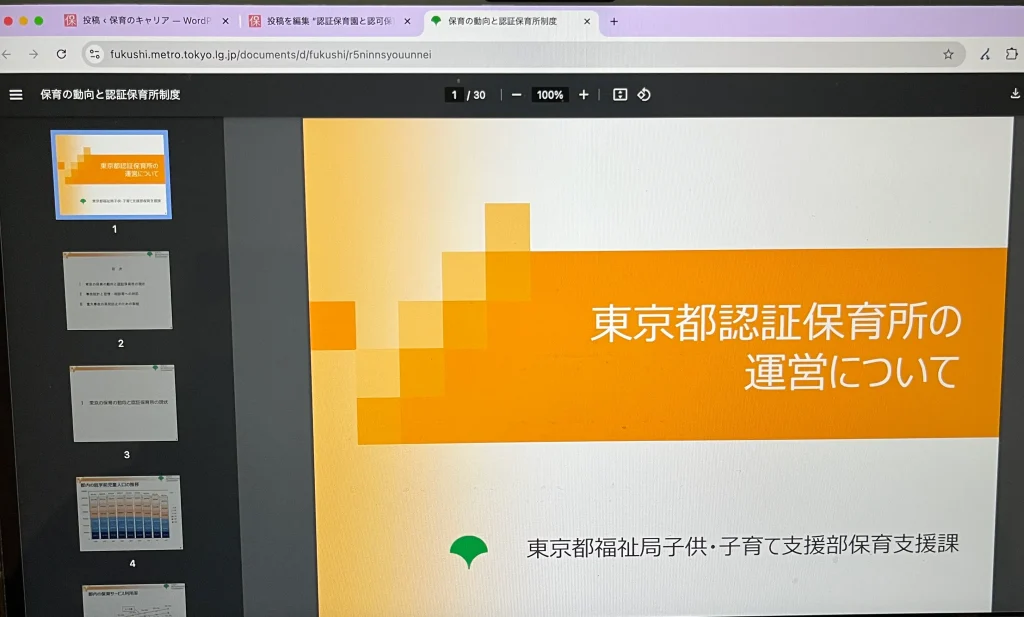
認証保育園と認可保育園とは?
保育施設の中には認可保育園とよく似た響きを持つ、認証保育園という施設形態があります。
名称が似ているため混同してしまう方もいますが、保育施設の特徴は明確に異なります。
ここでは、保育士の多くが就業している認可保育園という保育施設について触れた上で、認証保育園についてご紹介していくのでぜひ参考にしてください。
認可保育園は国が定めた基準を満たした児童福祉施設
認可保育園は国が定めた基準を満たし、児童福祉法に基づいて運営される保育施設です。
厚生労働省が示す「保育所保育指針」に従い、園舎の面積や保育士の配置基準、設備などが厳しく定められています。
規定の基準を満たした施設には自治体から補助金が支給されます。
この補助金によって、施設の運営が安定し、保護者が負担する保育料も抑えられる仕組みになっています。
さらに、保育料は家庭の所得に応じて段階的に設定されることが多く、低所得世帯でも利用しやすい制度が整っています。
つまり、保護者にとっては、利用料が比較的安価であり、安心して子どもを預けられる環境が整っている点が魅力です。
一方、利用するには「保育を必要とする理由」を自治体に証明する必要があります。
例えば、就労証明書や求職活動を証明する書類などを提出することが一般的です。
認証保育園は東京都が定めた一定の基準を満たした保育施設

認証保育園は東京都が独自に定めた基準を満たす保育施設のことです。
国の認可保育園とは異なる制度で、東京都が待機児童問題に対応するために導入した仕組みです。
東京都では共働き世代が増加し、待機児童が増えました。
この待機児童を解消することを目的に、2001年に都市特有の保育ニーズに対応できる認証保育園が創設されました。
<認証保育所の特色>
引用:東京都福祉局「保育の動向と認証保育所制度」
○ 保育を必要とする全ての人が対象
○ 0歳または、1歳児定員を必ず設定
○ 低年齢児(0~2歳児)の定員を必ず5割以上設定
○ 13時間以上の開所
○ 利用者と保育所の直接契約
○ 保育料は一定の上限の範囲内で自由に設定
○ 都独自の基準を設定し、適切な保育水準を確保
認証保育園は、東京都福祉局の基準に基づき、A型とB型の2種類に分かれています。
| A型 | B型 | |
|---|---|---|
| 設置主体 | 民間事業者等 | 個人 |
| 対象 | 0〜5歳 | 0〜2歳 |
| 規模 | 20〜120名 | 6〜29名 |
| 設置基準 | 3.3平米 | 2.5平米 |
| 園庭 | 設置 | 規定なし |
どちらの施設も面積や職員配置基準は、国の認可保育園と違い都独自の要件で、一定の保育士資格者の配置が求められるほか、安全性を確保する基準も設けられています。
利用者にとっては、比較的申し込みのハードルが低いことが魅力です。
例えば、認可保育園で必要な「就労証明」などの書類提出が不要な場合があり、保育を必要とする理由を問わず利用しやすい制度となっています。
ここからは、A型とB型の違いを詳しくご紹介するのでぜひ参考にしてください。
A型は最寄り駅から徒歩5分以内の場所に設置される
A型の認証保育園は東京都が定めた基準に基づき設置された保育施設で、0〜5歳児を対象とし、定員は20〜120名です。
駅から徒歩5分以内という立地基準を満たすことで補助金が支給されるため、基本的に駅近に設置されています。
施設には園庭が設置されていること、もしくは近隣に代替となる公園があることが必須条件です。
A型では広い年齢層の子どもを保育する経験が積めるほか、通勤の利便性も高い環境で働くことができます。
B型は定員が少ないため少人数を対象に保育できる
B型の認証保育園は0〜2歳児が対象で、定員は6〜29名と小規模な保育施設です。
保育士が子ども一人ひとりの成長にじっくりと関わることができます。
設置主体は個人経営が多く、ビルのワンフロアやマンションの一室を利用するケースが一般的で、園庭の設置義務はありませんが、近隣の公園を活用することが多いです。
乳児保育に特化していますが、職員数が少ない場合には業務負担が増えることもあるため、職場の体制を確認することが重要です。
認証保育園と認可保育園の特徴の違いを比較
認証保育園の特徴は認可保育園とさまざまな点で異なります。
転職を検討している保育士は認証保育園と認可保育園の違いを明確にした上で、自身に合った特徴を持つ保育施設を検討しましょう。
以下の表では、認証保育園と認可保育園を6つの項目で比較しています。
| 認証保育園 | 認可保育園 | |
|---|---|---|
| 運営母体 | A型:民間事業者 B型:個人 | 自治体もしくは民間事業者 |
| 定員 | A型:20名〜120名 B型:6〜29名 | 20名以上 |
| 0歳児保育 | 義務付けられている | 施設によっては0歳児枠はない |
| 開園時間 | 13時間以上 | 11時間以上 |
| 保育士の配置基準 | 有資格者は6割以上 | 有資格者の配置基準は以下のとおり。 0歳児3名あたり1名1・2歳児6名あたり1名3歳児15名あたり1名4歳児以上25名あたり1名 |
| サービス内容の説明 | 契約の際に保護者に対して重要事項説明書の配布とサービス内容 施設概要 事業者概要の説明が義務付けられている | 義務付けられていない |
認証保育園は0歳児保育が義務付けられている
認証保育園は0歳児保育が義務付けられています。
これは保護者の乳児期の保育ニーズに対応するため、A型・B型ともに定員内に必ず0歳児枠を設ける必要があると定められているからです。
ただし、例外的に0歳児を設定しなくてもよいケースもあります。
ただし、1歳児の定員を設定する施設においては、区市町村が認める場合に限り、0歳児の定員を設定しないことができる。
引用:東京都福祉局「東京都認証保育所事業実施要綱」
認可保育園の場合では1歳児以上の保育に特化している施設も多く、0歳児の受け入れがないケースがあります。
特に、0歳児は発達段階が著しく、ミルクや離乳食、睡眠など、年齢に応じたケアが求められるため、認証保育園で働くことで乳児保育の専門スキルを身につけることができます。
就労義務がなく保育を必要とする幅広い方が利用している
認証保育園は就労義務がなく、幅広い家庭環境の保護者が利用できることが特徴です。
認可保育園では保護者が「保育を必要とする事由」を証明する必要があり、就労状況や求職中であることが条件となります。
一方、認証保育園は都独自の基準で運営されているため、このような条件が緩やかです。
例えば、パート勤務や在宅勤務の保護者だけでなく、育児負担を軽減したい家庭や短期間だけ保育を必要とする家庭なども利用しやすい仕組みになっています。
つまり、認証保育園ではさまざまな家庭環境の子どもたちと関わる機会があるということです。
保育士にとっては、子ども一人ひとりの状況に合わせた柔軟な保育が求められるため、家庭全体を見守る視点や多様なニーズに対応する力が身につくと考えられます。
認証保育園での働き方
認証保育園は都独自の保育施設のため、働き方にも特徴があります。
仕事内容は他の保育施設と大きく変わりませんが、都独自の基準を満たした開園時間や配置などの特色を理解しておきましょう。
- 基本的な仕事内容は他の保育施設とほとんど同じ
- 夜間保育を実施しているためシフトによっては20〜22時まで働く
- 早番・中番・遅番のどこかで1日8時間勤務する
- 園の職員配置によっては無資格でも常勤で働くことができる
ここでは主なポイントを挙げつつ、認証保育園で働く前に知っておきたい懸念点についても触れていきます。
基本的な仕事内容は他の保育施設とほとんど同じ
認証保育園の仕事は、他の保育施設と大きな違いはありません。
主な保育内容は、以下のとおりです。
- 食事介助
- 排泄介助
- 着替え補助
- 保護者対応
- 行事の企画
- 書類作成 など
子ども一人ひとりの成長や個性に合わせて指導計画を立てる点も、認可保育園と共通しています。
ただし、小規模な園では職員数が限られるため、一人の保育士が複数の業務を担当する場合があります。
そのため、柔軟な対応力や幅広い業務への適応が求められることが多いです。
夜間保育を実施しているためシフトによっては20〜22時まで働く
認証保育園では夜間勤務が発生する場合があります。
開園時間が13時間以上と長いため、なかには早朝から深夜にかけて営業している園もあります。
特に、夜間保育を行う施設は保護者の帰宅時間に合わせてシフトが組まれるため、遅番の勤務が20時から22時までになることも珍しくありません。
その結果、勤務時間が不規則になりやすい点が特徴です。
例えば、夜間帯は以下の業務が中心になります。
- 食事後のケア
- 就寝準備
- 保護者への引き渡し
保育士として夜間保育を担う場合は、生活リズムの管理が大切です。
体調を維持するためには、日中にしっかりと休息を取ることが欠かせません。
また、自分がどの時間帯の勤務に対応できるかを事前に考慮し、転職先の勤務体制を確認すると安心です。
早番・中番・遅番のどこかで1日8時間勤務する
認証保育園の勤務は、早番・中番・遅番のいずれかで1日8時間が基本です。
実際に、認証保育園の求人を保有する保育士転職サイトで確認してみても、開園時間のうち実働8時間のシフト制が多いです。
早番は朝7時や8時から始まり、日中のメイン保育を担当します。
中番は10時頃から19時頃までの勤務が一般的です。
遅番は13時や14時から22時頃までを担当しますが、園の開園時間により変動する場合があります。
また、平日だけでなく土曜保育を行う園も多く、土曜日の勤務が発生する可能性もあります。
年間休日や週休二日制の有無は、働きやすさに直結するため、転職時に確認することが重要です。
園の職員配置によっては無資格でも常勤で働くことができる
認証保育園では、職員配置基準により無資格でも常勤で働くことが可能です。
具体的に、認可外保育園で働く職員の3分の1ほどが保育士もしくは看護師の資格が必要です。
保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設及び(1)における1人が配置されている時間帯にあっては 1人 以上は 、) 、保育士又は看護師の資格を有する者であること。
引用:文部科学省「認可外保育施設指導監督基準」
つまり、3分の2ほどの職員は保育士資格がなくても働くことができます。
一般的な保育施設では、無資格者は「保育補助」として働くケースが多いです。
保育補助の仕事は、食事の準備や掃除、子どもの身の回りのサポートなど、直接的な保育業務を補助する内容が中心です。
一方で、認証保育園では保育補助に留まらず、子どもの世話を担当する場合もあり、保育士としての経験を積みやすい環境といえます。
また、資格取得支援を行っている園もあり、働きながら保育士資格を目指せる環境を提供していることが特徴です。
無資格でスタートする場合でも、将来を見据えてスキルアップできる職場を選ぶとよいでしょう。
こうした支援制度があるかどうかは、転職時に事前に確認することが重要です。
認証保育園で働くメリット
認証保育園は都市特有の保育ニーズを満たす運営がされているため、保育士にとっても他の保育施設にはないメリットがあります。
実は、認証保育園には最寄り駅から徒歩5分圏内にあることや、少人数を対象に保育ができること以外にも以下のようなメリットがあります。
認証保育園で働きたい方は、どのようなメリットがあるのか詳しく理解しておきましょう。
パートや契約社員などが柔軟に働きやすい
認証保育園では、パートや契約社員などが柔軟に働くことができます。
これは開園時間が長く、早朝や夜間、短時間勤務など、シフトの選択肢が豊富だからです。
そのため、育児や介護など家庭の事情に合わせた働き方がしやすい環境です。
例えば、保育士資格を持つ方は、朝の数時間だけ働く勤務や週2〜3日の勤務を認める園もあります。
また、契約社員やアルバイトとして働ける雇用形態を設けている園も多いです。
以下の表では、認証保育園の求人を保有している保育士転職サイトをまとめているのでぜひ参考にしてください。
| 認証保育園の求人数 | 転職サポートの有無 | |
|---|---|---|
| 保育士ワーカー | 128件 | あり |
| 保育士バンク | 431件 | あり |
| マイナビ保育士 | 741件(認定保育園を含む) | あり |
| ジョブメドレー保育 | 10,808件(認可保育園を含む) | なし |
| ほいくジョブ | 853件 | あり |
| ほいくisお仕事探し | 1,119件(認定保育園を含む) | なし |
| 保育のお仕事 | 1,068件(認定保育園を含む) | あり |
| 保育士コンシェル | 251件(認定保育所を含む) | あり |
※認証保育園の求人数は2025年12月6日時点の情報を参考にしています。
認証保育園の求人を多く保有する転職サイトから職場を検討すると、より自身のライフスタイルに合った認証保育園で働きやすいですよ。
英語やリトミックなど専門的な保育スキルが身に付く園もある
認証保育園には専門的な保育スキルが身につくことがあります。
なぜなら、保護者の多様なニーズに応えるため、特色あるカリキュラムを取り入れている園が多くあるからです。
例えば、英語のレッスンではネイティブ講師が園に訪問し、子どもたちと歌や会話を楽しむプログラムが導入されることがあります。
生活の中で、日本語と同じように英語に触れる、浸ることで、自然と英語を発することが出来るようになります。毎日職員と講師と楽しく英語に触れ、英語への抵抗感を作ることなく将来の可能性を広げています。
引用:株式会社日本保育サービス「アスク バイリンガル保育園 浅草橋」
上記は保育園運営の大手である株式会社日本保育サービスが運営する認証保育園「アスク バイリンガル保育園 浅草橋」が実施する学習プログラムです。
また、リトミックを実施する保育園では音楽に合わせた身体表現を通じて、リズム感や表現力を育む活動が行われます。
そのほかにも、体操やアート制作など、専門的なプログラムを取り入れている園も多いです。
こうしたカリキュラムに力を入れることで、他園との差別化を図っているのが認証保育園の特徴です。
保育士として新たなスキルを習得したい方にとっては、こうした環境で働くことは大きなメリットになります。
また、これらの経験は転職活動の際に強みとしてアピールできるため、キャリアアップにもつながります。
保育士として柔軟な対応力が身に付きやすい
認証保育園では、保育士として柔軟な対応力が身に付く環境が整っています。
なぜなら、多様な家庭背景がある0〜5歳までの子どもを保育することが多いためです。
また、家庭環境が共働き家庭、シングル家庭、在宅勤務家庭など、それぞれ異なるライフスタイルを持つ保護者との連携が求められます。
そのため、保育士としては、年齢や発達段階ごとの保育だけでなく、家庭環境に応じた柔軟な対応が必要です。
こうした多様な経験を通じて、保育士としての観察力や対応力が大きく向上します。
特に、未経験の保育士にとっては、多彩な役割を経験できることで、保育の現場全体を把握する力が養われます。
認証保育園で働くデメリット
認証保育園は働きやすい面がある一方で、国の認可外施設ならではの課題もあります。
ここでは、認証保育園で働く際に知っておきたい以下のようなデメリットについてご紹介していきます。
処遇改善手当の対象外だったり、職員数が足りなくなると負担が偏りやすいなどの懸念があるため、事前に理解しておきましょう。
認可外保育に分類されるので処遇改善手当の対象外となる
認証保育園は処遇改善加算の対象外であるため、給与アップが難しい場合があります。
これは、認証保育園が東京都独自の制度であり、国の制度上は「認可外保育施設」に分類されるためです。
園によっては独自に処遇改善を実施したり、ボーナス支給を行うところもありますが、国の補助金が受けられる認可保育園に比べると、補助金の有無で大きな差が出る点は否めません。
長時間保育や延長保育で業務負担が大きくなることがある
長時間保育や延長保育に対応している認証保育園は、一人あたりの業務負担が大きくなることがあります。
特に、都心部の認証保育園は働く保護者の多様なニーズに応えるために、開園時間が早朝から夜遅くまで設定されることが一般的です。
例えば、認証保育園に分類されるマミーズエンジェル中野白鷺保育園では7時30分から22時まで開園している場合があります。
7:30 ~ 22:00 (基本時間は7:30~20:30まで)
引用:株式会社マミーズエンジェル「施設のご紹介|中野白鷺保育園」
延長保育を実施している園では、夜間帯に子どもの寝かしつけや保護者への引き渡しを行う業務が加わります。
その結果、保育士のシフトが複雑化し、一人ひとりの業務負担が増える場合があります。
特に、夜間帯に十分な人員を確保できない園では、負担が集中しやすい点が課題です。
小規模園では一人あたりの負担が増えることがある
小規模な認証保育園では、一人あたりの業務負担が増えることがあります。
特に、B型の認証保育園は職員数が限られているため、一人が以下のように複数の役割を担う場面も少なくありません。
- リーダー業務
- 保護者対応
- 書類作成
- 清掃や備品管理など
保育士によっては子どもとしっかり向き合う時間が十分に確保できないと感じる可能性もあります。
ただ、小規模な認証保育園ならではの利点として、家庭的な雰囲気の中で子ども一人ひとりと深く関わる機会が多い点が挙げられます。
このため、業務が効率よく分担されている園では、子どもとの関係性をじっくり築ける環境になることもあります。

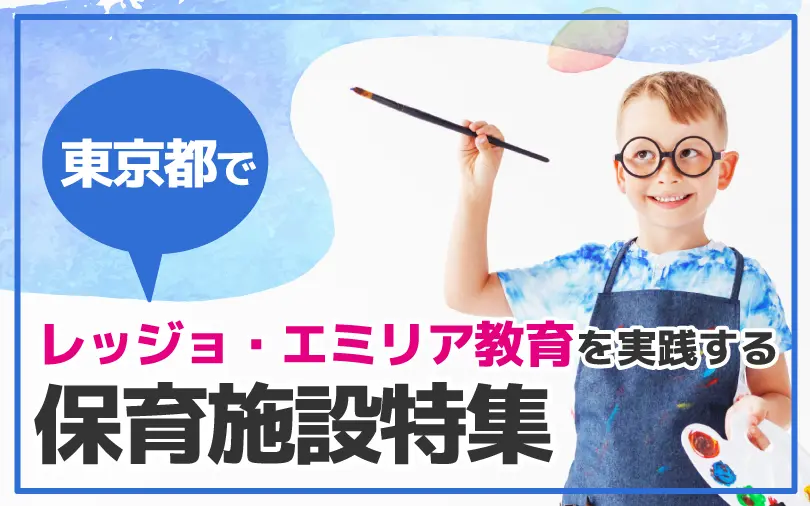



本記事へのコメント